アイキャッチとは、目を引くものという意味です。
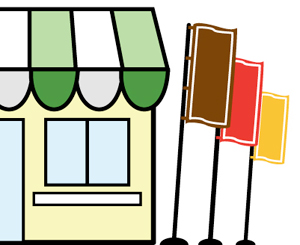
のぼり旗は人に見てもらうために設置する物なので、アイキャッチにもこだわって作る必要性は高くなります。注意を惹くことに主眼を置いてデザインを考えれば、ありきたりな物にはならないので効果的なのぼり旗を作ることができるでしょう。
例えば、色の使い方はそのうちの一つです。
周囲に埋没してしまう色だったとすれば見逃されてしまいますが、反対色を活用することで目を引くことが出来ます。
また、イラストやロゴなどを取り入れて、そのお店がどんなものかアピールできれば注意を引くことが可能です。
他にものぼり旗の立て方を変えたり、形を工夫することでも注意を引けるはずです。
のぼり旗専門店では、作り方のアドバイスをしてくれるので、作り方で悩んだ場合は相談すると良いです。場合によってはデザインの作り方のイロハの記事を載せているところもあるので、目を引きつけるコツを掴むことができます。
一つだけ言えることは、適当にやっても上手くいかないことです。街中にあるのぼり旗もこの点を意識した物が多いので、デザインの参考に確認してみても良いでしょう。自分の製作に活かすことができます。
目で追うという習性を活かして作ろう
人は、目で追う習性があるので、その習性を活かすことも効果的です。具体的には、人は動いている物に目が自然と行くようになっています。
のぼり旗は風になびいて動いているので、まさに自然と見てしまいます。そこで、文字イラストを使って短時間で宣伝したいことを折り込めば、効果的にアピールすることが可能です。
もちろん目を引いたとしても印象に残らなければなりませんし、見づらいと感じられてしまえばそれ以上の効果に期待はできないため、全体的な色使いや視界に入る場所に設置すること、大きさを視認できるレベルにすることなどにも注意してデザインしていきます。
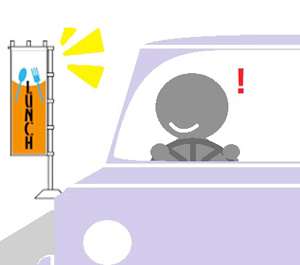
これも、自分の立場に立って考えてみれば具体化していきやすいです。街中で見やすい、印象に残ったと感じたのぼり旗がどのように作られていたのかを元にすれば、注意を引く物を作ることが可能です。
見本も沢山見て、一般的に活用されている物に共通するのは何かも考えてみると良いでしょう。
こうした作業は時間がかかりますが、きちんと理にかなったデザインを考えられるようになるので、ぜひ実践することをおすすめします。それでこそ、宣伝をするためにのぼり旗を設置する意味が出てきます。